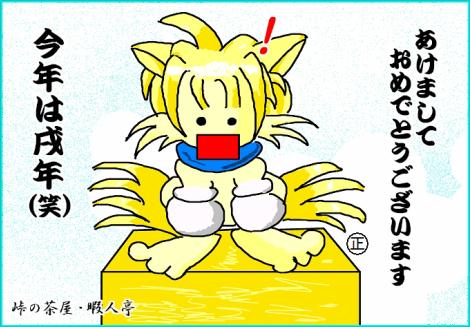
「峠の茶屋・暇人亭」の正山竹紀さんからの年賀画像です。
元があまりにも重いためメールソフトが受信拒否起こして、ウェブメールでサルベージしたとゆー事実は、この際忘れて差し上げましょう(おひ)。
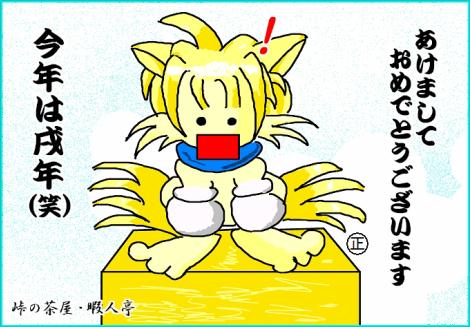
画像だけでメッセージは無かったので、何の関係もなく店主作・干支川柳をどーぞ。毎度の如く故事成語にちなんでいます。
・犬に論語
(「いくら価値の高いものでも、価値を知らない者は有難さが分からない」という意味。「猫に小判」「豚に真珠」より即物性が薄いかなーとも思う)
論語より 有難がらぬ リグ・ヴェーダ
※リグ・ヴェーダはバラモン教の、後にはヒンドゥー教の聖典。東アジアの犬には全然有難くないだろう。
・犬も歩けば棒に当たる
(「不意にひどい目に遭わされる」という意味。中世〜近世の日本には野犬が多く、しばしば棒で打たれるどころか狩り出されて食用にされていたが、食品としては低級であったため、正式の食事には一切出されなかったというのは余談)
棒に当て 店で捌くは 樊[口+會](はんかい)か
※樊[口+會]は約2200年前の武将で、前漢の初代皇帝となった劉邦(高祖)に仕えていた。元の職業は犬肉屋。
・狡兎死して走狗煮られる
(先述の劉邦に仕えた武将の韓信が、漢の天下統一後に濡れ衣を掛けられ処刑された直前に残した言葉という。「役割の無くなった武将は危険だから始末される」という意味)
韓信は 親父煮るより 旨かろう
※劉邦はかつて、項羽に父親を人質に取られ、
項羽「これでも降伏しないなら、お前の親父を煮殺すぞ」(←当時の中国では、「不孝≒究極の人でなし、人非人」だった。……少なくとも人質を取るよりも)
劉邦「俺とお前は義兄弟。つまり俺の親父はお前の親父も同然だろ。まあどうしても自分の親父を煮殺すっていうのなら、そのスープを俺にも分けてくれ」(←つまり、煮殺せば劉邦を人でなしにできるが、手に掛けた項羽はどうしようもない人間の屑になる)
という展開があった。ちなみに項羽は人を煮殺す趣味があるっぽいが、劉邦はそんな事はない。
・羊頭狗肉
(「看板(表向き)は立派だが中身は伴わない」という意味。古代中国では犬肉は高級食材だったが、遊牧民の羊珍重の風俗が五胡十六国時代以降広まり犬肉の価値が低下したため、この格言ができたのはそれ以降だろう)
・鶏鳴狗盗
(「下らない連中でも一応は役に立つ事もある」という意味。戦国時代、斉の孟嘗君の取り巻きのこそ泥と鳴き真似男が秦からの脱出を手助けした事に由来する)
ちょっと待て 使い回しは ネタ枯渇
※すみません。